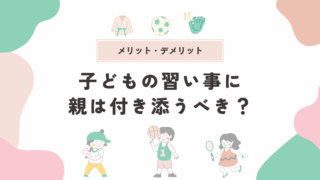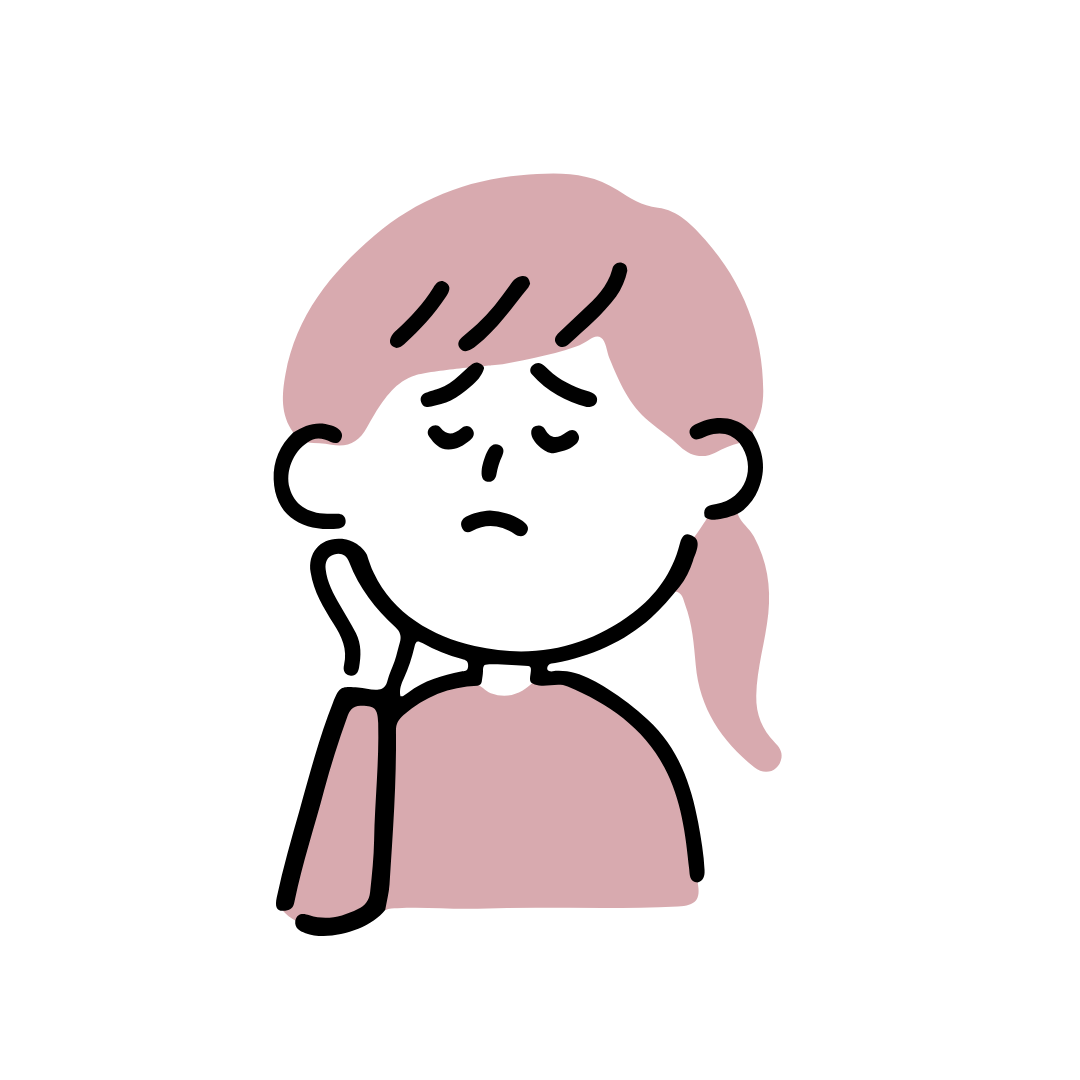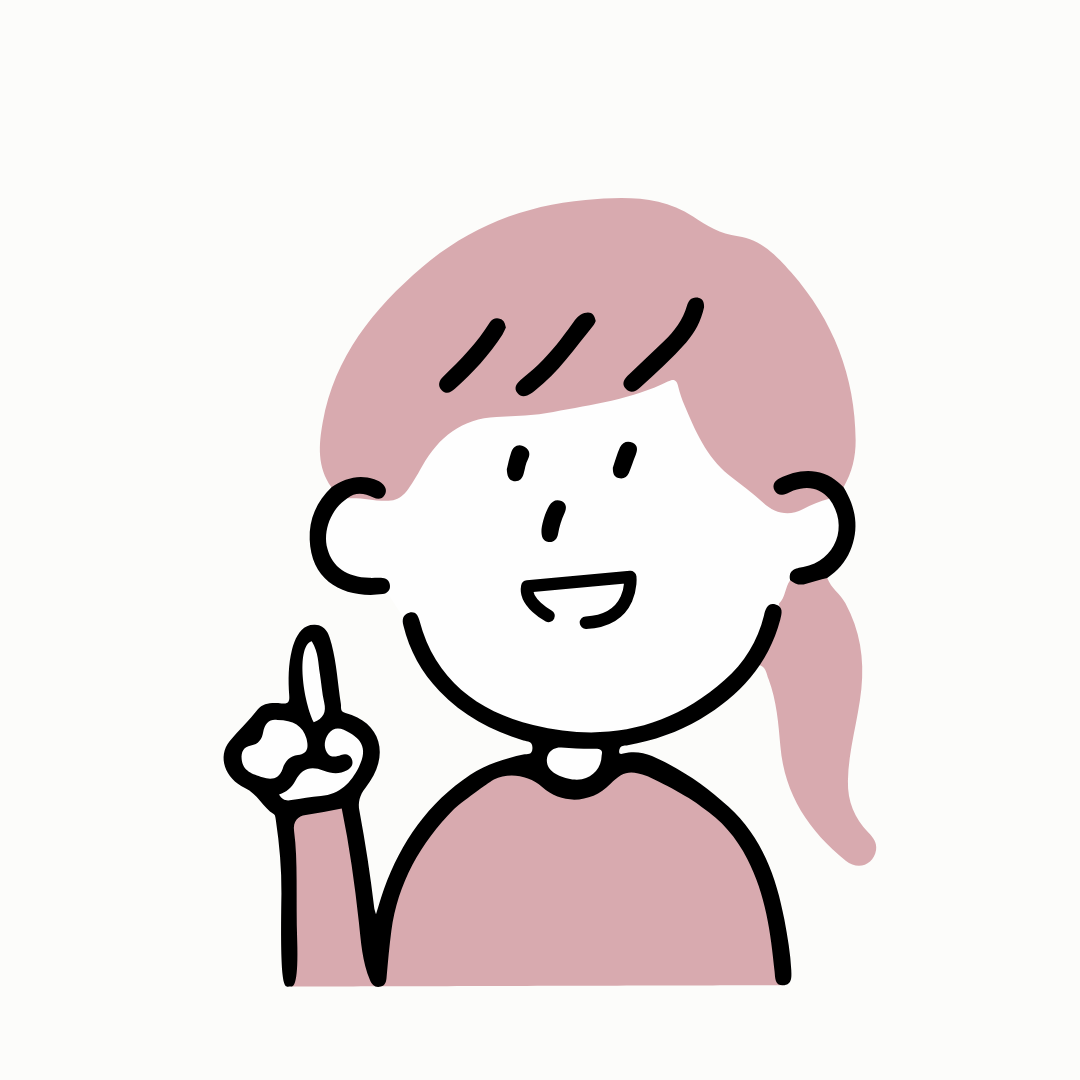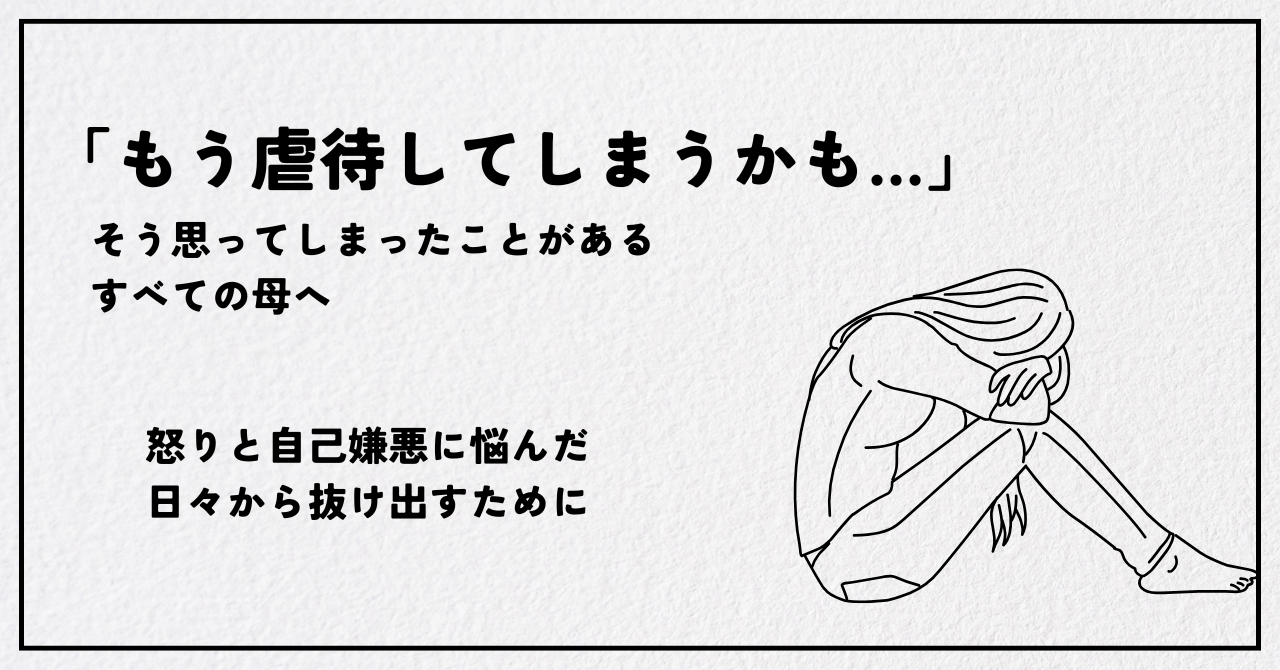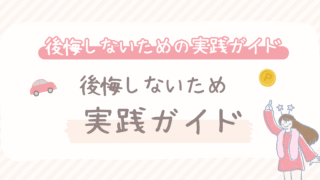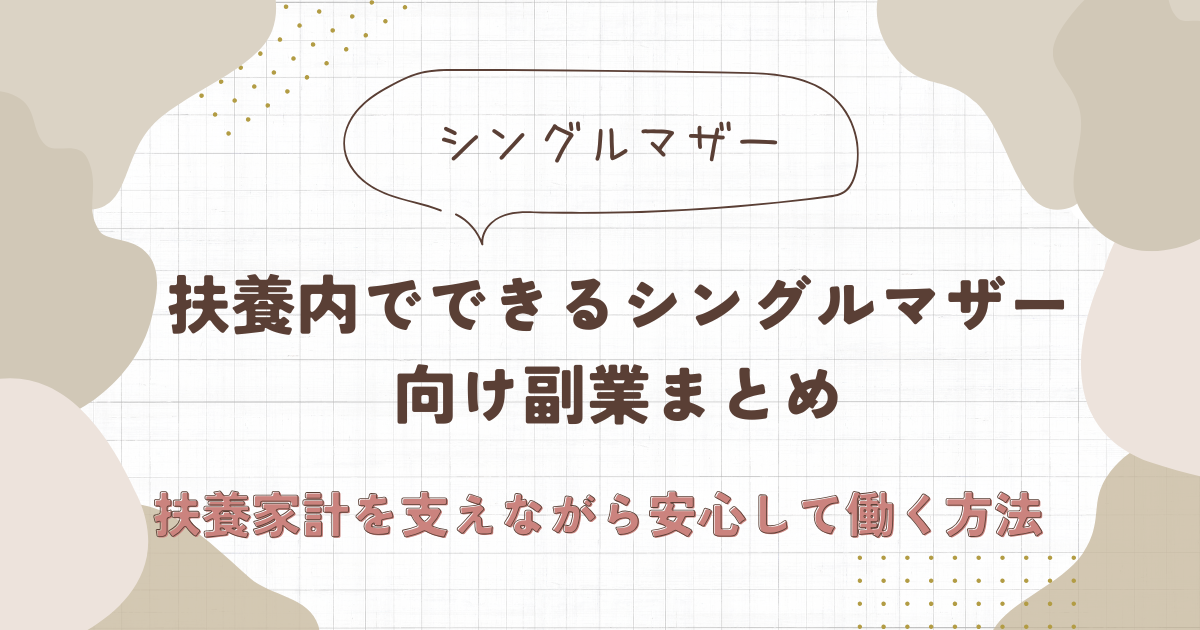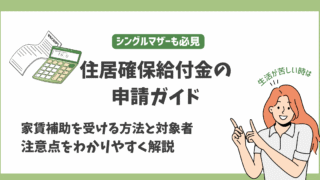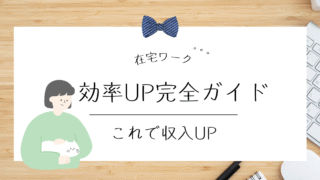はじめに|なぜ今「デジタルとの付き合い方」が重要なのか
スマホやタブレットが生活に浸透した今、子どもたちは日常的にゲームやYouTubeと触れ合っています。 一方で、保護者の多くが「つい見せてしまう」「止め時がわからない」と悩みを抱えているのが現実です。
厚生労働省が公表した調査によれば、小学生の約8割がインターネットを利用しており、その多くが動画サイトやゲームアプリを通じてデジタルコンテンツに触れています(※出典:厚生労働省「青少年のインターネット利用環境実態調査」)。
そこで本記事では、家庭で実践できるゲーム・YouTubeとの「ちょうどいい付き合い方」として、我が家のルールと工夫を紹介します。SEOキーワード「ゲーム時間制限」「YouTube 子どもルール」「スマホ依存防止」などを意識しながら、読者が参考にしやすいよう構成しています。
筆者も、スマホ問題には頭を抱えています。制限しすぎるのもお友達とやりとりを遮断してしまうと良くないし…。かといって、好き放題にスマホをいじっているのもどうかと思うし…。

子どもとゲーム・YouTubeの付き合い方でよくある悩み
- 時間制限が守れない
- 「あと5分」と言いながら、ずるずると見続けてしまう。
- タイマーを使っても“終了の区切り”が曖昧だと、子どもはまだ見たい気持ちを優先しがちです。習慣化されたルールがないと、毎回トラブルになります。
- 親がいない間に長時間見てしまう
- 留守中のルールが曖昧で、気づけば数時間経過していることも。
- スマートフォンやタブレットが自由に使える場所にあると、子どもは誘惑に勝てません。タイミングと場所の管理が必要です。
- やめさせようとすると癇癪を起こす
- 「まだ終わってない!」「あとちょっと!」と強く反発される。
- 自分の意志でやめる経験がない子ほど、突然の終了に強いストレスを感じて怒りに変えやすくなります。
- 学力・睡眠・生活リズムへの悪影響が心配
- ゲームや動画優先で宿題や就寝時間が後回しに。
- 生活リズムが崩れると、集中力や情緒の安定にも悪影響が出やすくなります。平日と休日でのメリハリをつける工夫が大切です。
- 親がつい使わせてしまう
- 自分の家事や仕事のために、“便利な預け道具”として使ってしまう。
- 忙しいときほど「静かにしていてくれるなら…」と手渡しがちですが、それが“ご褒美”になると使用頻度がどんどん増えてしまう悪循環に陥ります。「2歳未満にはスクリーン使用を推奨しない」としたうえで、年齢に応じたメディア利用時間と“対面でのやりとり”を重視すべきとしています(出典:日本小児科学会「子どもとメディア」ガイドライン)。
我が家で実践しているゲーム・YouTubeのルール
ゲームやYouTubeとの付き合いは“ゼロにする”ことではなく、“どう向き合うか”が大切です。我が家では、ただ制限するのではなく、子どもと一緒にルールを考えるスタンスを大事にしています。そのうえで、以下のような具体的な工夫を取り入れています。
| ルール内容 | 補足説明 |
|---|---|
| 平日は1日30分以内 | 食事・宿題・片づけが終わってから。守れなければ翌日は無し。 |
| 週末は最大1時間(午前30分+午後30分) | 学校が休みの日でもダラダラしないよう時間を分ける工夫。 |
| 「見る前にやることリスト」を貼り出す | 見る前に宿題・手伝い・連絡帳のチェックを終わらせるルーチンを定着させる。 |
| 見るコンテンツは事前に話し合いで決める | 年齢に合わない動画・暴力的なゲームを避けるため、事前チェックとフィルタリングを徹底。 |
| 「あと5分タイマー」は子ども自身が操作 | 自分で終了時間を意識させ、自律を促す練習に。 |
ポイントは「親が勝手に決めないこと」。一方的な制限ではなく、子どもと話し合って決めたルールは“守る意味”を実感しやすくなります。
我が家は、小5と小4なので1時間。年齢が上がるにあたり時間も増やしています。家庭の状況や年齢にもよって変わってきます。お子さんの年齢と現状を見極めるのもポイント。
スマホ・ゲーム依存を防ぐためのチェックポイント
まずは、お子さんが“依存的”な使い方になっていないかを確認するための簡易チェックから始めましょう。
スマホ・ゲーム依存チェックリスト(親向け)
- □ ゲームやYouTubeを止めるとすぐにイライラしたり、暴言を吐く
- □ 家族との会話よりも画面を優先することが増えた
- □ 学校や習い事に集中できず、宿題に手がつかない
- □ 夜遅くまで画面を見ていて睡眠時間が減っている
- □ 外遊びや趣味に関心を示さなくなった
- □ 注意しても隠れて見ようとする
3項目以上当てはまる場合は“依存の入り口”にあると考え、使用時間の見直しや声かけの方法を工夫するサインです。
使用時間を「見える化」するグラフの活用
子どもは“時間感覚”が未発達なため、「何分使ったか」が分かりにくい傾向があります。
そこで我が家では、【週ごとの記録グラフ】を取り入れて、親子で「使いすぎていないか」を一緒に振り返るようにしています。
使用時間の記録グラフ(例:1週間分)
| 曜日 | 使用時間(ゲーム+YouTube) | コメント |
| 月曜日 | 25分 | ルール内、スムーズに終了 |
| 火曜日 | 45分 | タイマー後に5分だけ延長 |
| 水曜日 | 30分 | 宿題の後、約束を守ってOK |
| 木曜日 | 60分 | 留守中に多めに使っていた |
| 金曜日 | 35分 | 習い事後にゆったり視聴 |
| 土曜日 | 90分 | 午前と午後をしっかり分けた |
| 日曜日 | 60分 | 家族で動画視聴、内容も良好 |
ポイントは「叱るため」ではなく「ふり返るため」に使うこと。 子どもが自分でバランス感覚を学べるよう、視覚的にわかるツールが効果的です。
習慣化のサポート法
家庭内でのルールを継続するには、“その場しのぎの制限”ではなく「習慣として根付かせる工夫」が必要です。以下に、我が家で取り入れている習慣化の仕組みをご紹介します。
● 見る前・見た後のルーティンを決めておく
- 例:見る前に→宿題/手伝い/次の日の準備 → 見終わったら→タイマー止め/記録記入/片づけ
- 手順化することで「見ていい時間」と「終わった後」の行動が明確になり、次第に自律的な習慣につながります。
● 一週間ごとのポイント制を導入
- 毎日ルールを守れたらシール/ポイント1つ→週末に好きな遊び時間10分追加など
- 遊びの中に“成功体験”を取り入れることで、「守った方が得だ」と子ども自身が気づくようになります。
● 毎週末に親子で振り返る時間を作る
- グラフを一緒に見ながら「どの日がよかったか」「どんな工夫をしたか」を対話します。
- 一緒に話す時間を持つことで、ルールが「押し付け」ではなく「成長の道具」に変わっていきます。
習慣は“守らせる”より“続けたくなる仕組み”に。親のサポートは「監視」ではなく「並走」のイメージで行うと、子どもは前向きにルールを受け入れやすくなります。
ルールが崩れたときの対処法
どれだけ工夫しても、完璧に守り続けられることはありません。大事なのは「破られたこと」よりも「どう立て直すか」です。
● 叱るよりも“ふり返り”を
- 「昨日は見すぎちゃったね。どこが難しかったかな?」と“問いかけ”から始めることで、責めずに改善点を共有できます。
● ルールを見直すチャンスにする
- 崩れたときこそ「このルール、今のままで合ってるかな?」と、内容を見直すタイミングに。
- 成長や生活リズムの変化に合わせて、柔軟に調整することも大切です。
● 子どもが自分で再設定できるようにする
- たとえば「次はどうすればいいと思う?」と聞いて、自分で対策を考えさせること。
- 自分で決めたルールは、守る意識が高まりやすくなります。
親がイライラして感情的になると、子どもも「怒られないように隠れる」ようになります。“対話”を軸にしたリカバリーこそが、長い目で見たデジタルとの付き合い方に大切です。
YouTube視聴の工夫
YouTubeは子どもにとって魅力的なコンテンツがあふれる一方で、依存性や刺激の強い動画、広告などのリスクも伴います。だからこそ“見る内容”や“見方”を工夫することで、安全で有意義な時間に変えることができます。
● 見るチャンネルをあらかじめ親子で選んでおく
- 教育的な内容、年齢に合った安心感のあるチャンネルを事前に登録。
- 一緒に探すことで「どういう動画ならいいか?」の基準を共有できます。
● オフライン再生を活用する
- YouTube Premiumなどで広告なし&オフライン視聴にすることで、気づけば別動画…の“自動再生地獄”を防げます。
● 見た内容を話す習慣をつける
- 「今日見た動画、どんな内容だった?」と聞くことで、内容への意識と表現力も高まります。
- また、親が関心を持ってくれていると分かるだけで、子どもは安心して話してくれるようになります。
視聴ルールを“禁止”で縛るのではなく、“選び方”や“楽しみ方”を教えることで、子ども自身のメディアリテラシーも育ちます。

まとめ|ルールは“制限”ではなく“成長のサポート”に
子どもとゲーム・YouTubeとの付き合いにおいて大切なのは、頭ごなしの禁止ではなく「どう付き合っていくか」を一緒に考えることです。
ルールは守らせるものではなく、“守りたくなる仕組み”として工夫していくことで、子どもは自ら選び、自ら成長する力を身につけていきます。
親にとっても完璧である必要はありません。つい見せてしまう日も、うまくいかない週もあるでしょう。でも、そのたびに「じゃあどうする?」と話し合える家庭こそが、子どもにとって最良の環境になります。
我が家の工夫が、どこかのご家庭のヒントになれば幸いです。今日から、無理なく・前向きに、“我が家らしいルール”を見つけてみてください。