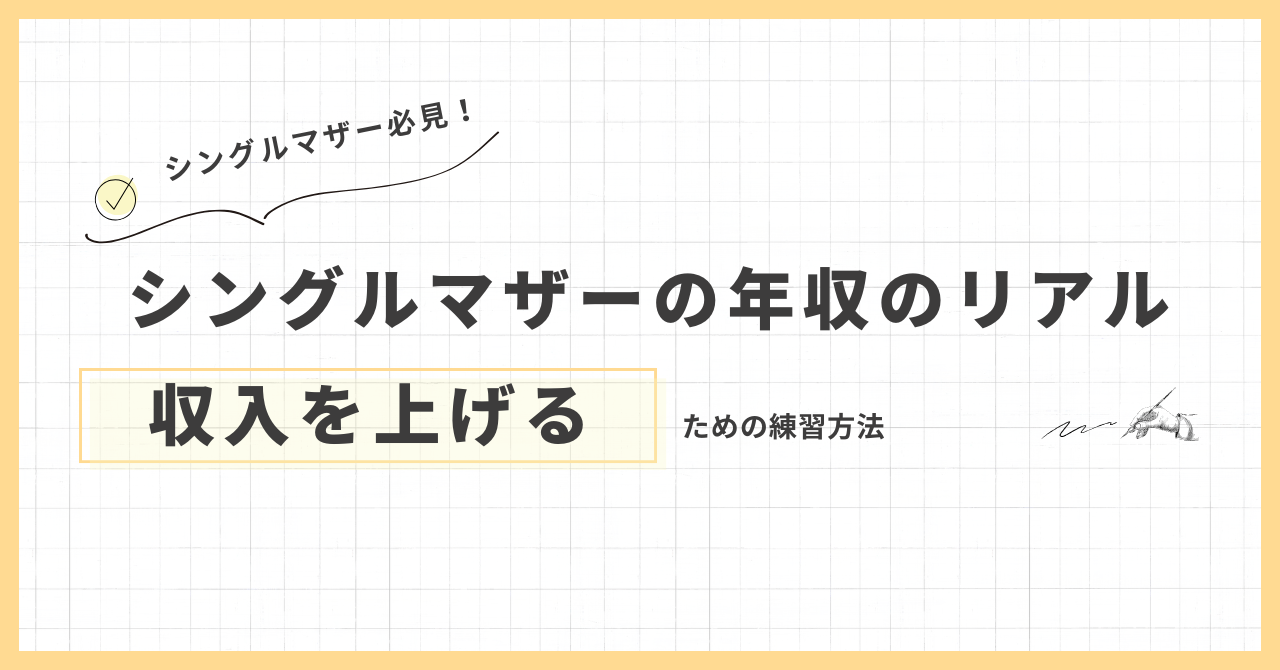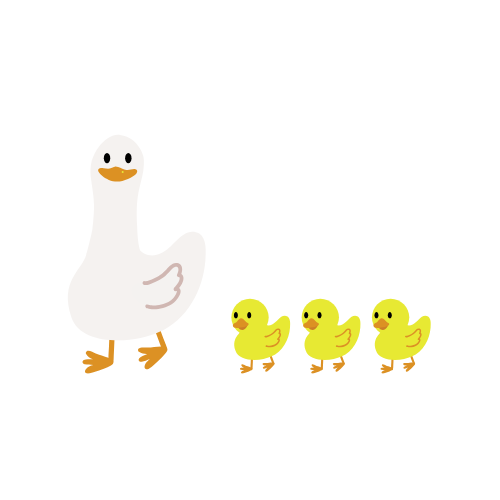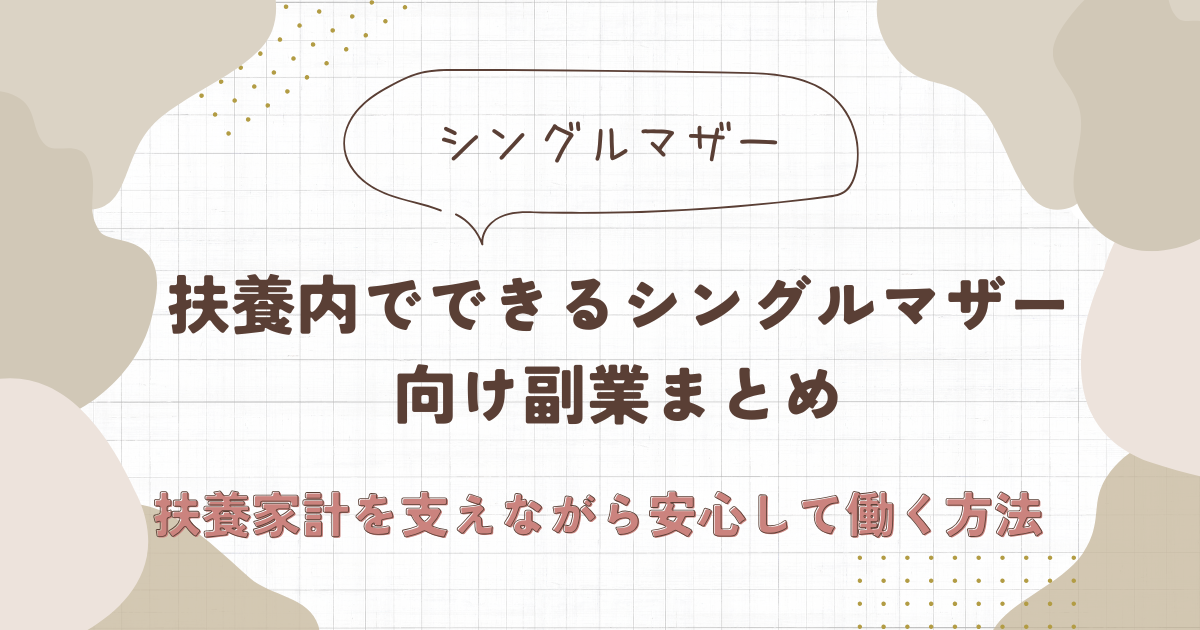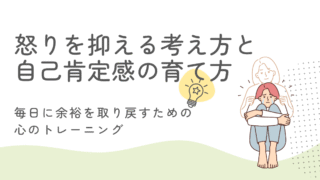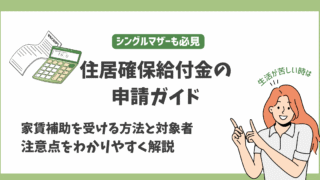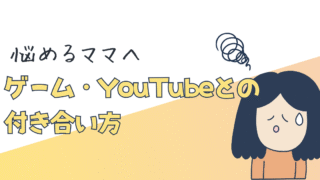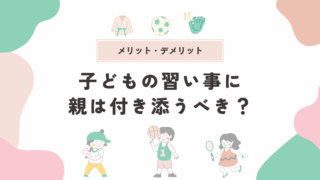1. はじめに
シングルマザーとして生きるということは、強さとしなやかさを求められる毎日の連続です。中でも”お金”は、日々の生活だけでなく、子どもの未来や自分自身の安心にも直結する重要な課題です。しかし、実際には「思ったより稼げない」「手当がいつまで続くかわからない」「収入を上げたいけどどうすれば…」という悩みを抱えている方が非常に多いのが現実です。
この記事では、最新のデータとともに、シングルマザーの収入のリアルと、それを少しずつ高めていくための”練習”的アプローチを解説します。

2. シングルマザーの平均年収と中央値(令和3年度データ)
現実的に、シングルマザーの多くは扶養を抜けてからの壁に直面します。育児と仕事の両立をしながら、十分な収入を得るのは簡単なことではありません。職場によっては理解が得られなかったり、保育園の送り迎えと勤務時間が合わなかったりと、物理的な壁も大きいのです。
フルタイムで働いて平均236万円という現実。それは決してあなたの能力が低いわけではありません。この社会が、まだ十分に“子育てと労働”を両立できるように設計されていないからです。
とはいえ、立ち止まってばかりもいられません。収入を補う支援制度、働き方の工夫、副業という選択肢。さまざまな視点からこの収入をどう活かし、どう伸ばしていくかを一緒に考えていきましょう。
「え?これだけ?」と驚いた方もいるかもしれません。実際にこの数字を見たとき、私は正直ショックを受けました。フルタイムで働いていても、これだけ?と思ってしまうのが本音です。でもこれが“現実”。ここから、どう工夫していくかが大事なんです。
母親自身の就労収入(厚生労働省 令和3年度 全国ひとり親世帯等調査より)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 平均年収 | 約236万円 |
| 中央値 | 約200万円 |
世帯全体の年収(手当・養育費・仕送り等を含む)
| 指標 | 金額 |
| 平均年収 | 約373万円 |
| 中央値 | 約300万円 |
出典:厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」
PDFリンク:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f1dc19f2-79dc-49bf-a774-21607026a21d/9ff012a5/20230725_councils_shingikai_hinkon_hitorioya_6TseCaln_05.pdf
雇用形態別の年収
| 雇用形態 | 平均年収(母親自身) |
| 正規の職員・従業員 | 約344万円 |
| パート・アルバイト等 | 約150万円 |
3. 年収の壁と制度の注意点
シングルマザーの年収に影響を与える「壁」はいくつもあります。例えば103万円の壁を越えると、親の扶養から外れてしまい、税制上の恩恵がなくなります。また130万円の壁を越えると、社会保険の加入義務が発生し、手取りが一気に減ることも。
そして一番厄介なのが、手当や支援制度が“段階的に減額”されていくこと。児童扶養手当などは、収入が少し上がっただけで支給額が大幅に下がることもあります。その結果、「頑張って働いたのに、結局手取りはほとんど変わらない」という状況に。
だからこそ大切なのは、制度を知り、自分のタイミングで“戦略的に”動くことです。副業を始めるタイミングを調整する、資格取得中は控除がある制度を利用する、社会保険の負担を見越して収入を増やすなど、制度と年収をセットで見ていく視点が必要になります。
“賢く生きる”とは、ただ働くだけではなく、社会の仕組みを理解し、自分の人生に役立てていくこと。その第一歩として、この年収の壁を冷静に見つめることがとても大切です。
「頑張れば頑張るほど手当が減っていくのがつらい」──そんな声をよく聞きます。実際、年収が200万円を超えたあたりから制度の恩恵が徐々に削られていくのは本当に悩ましいところです。“働くほど損”と感じる場面に出くわすのは、決して少なくありません。だからこそ、“賢く受け取る”知識も必要なのです。
| 年収の壁 | 内容 | 影響する制度例 |
| 103万円の壁 | 扶養控除の対象から外れるライン | 所得税控除、配偶者控除 |
| 130万円の壁 | 社会保険加入の義務が発生 | 健康保険・厚生年金 |
| 160~200万円 | 手当等の段階的減額が始まる | 児童扶養手当・保育料減免 |
| 260万円前後 | 支援制度の多くが受給不可になる | 住民税非課税、医療費助成、公営住宅など |
4. 年収を上げるための”練習”ステップ
ステップ1:支出の見える化
- 家計簿アプリやノートで固定費・変動費を整理
- 無意識の浪費ポイントを発見する
補足:”何に使ったか分からないお金”を見える化することが、最初の改善ポイントです。
ステップ2:制度のフル活用を調べる
- 市区町村HP、子育て支援窓口、LINE相談などを使う
- 自分が使える支援はすべて申請するつもりで調べる
補足:申請して初めて得られる支援がほとんど。”知っている”だけでは何も変わりません。
ステップ3:小さく学ぶ・試す
- YouTubeや無料講座で興味あることを見つけてみる
- 月1冊の読書、週に1時間だけの勉強など”練習”から始めてOK
補足:最初は”遊び感覚”でOK。気負わず、試しながら続けられる方法を見つけましょう。

5. 働き方別・収入比較
| 働き方 | 特徴 | 想定年収 | 向いている人 |
| パート・バイト | 柔軟な時間だが収入は低め | 100~200万円 | 低学年の子どもがいる、短時間しか働けない |
| フルタイム社員 | 安定するが拘束時間が長い | 250~400万円 | 保育環境が整っている、実家支援がある |
| 在宅ワーク | 通勤不要だが成果報酬も多い | 150~350万円 | PCスキルがある、自己管理ができる人 |
| 副業+パート | 柔軟性と収入バランスが良い | 250~500万円 | スキルを活かしたい人、時間を調整できる |
| 自営業・業務委託 | 成果次第で高収入も可 | 300~800万円 | 起業志向、マーケティングや販売が得意 |
どんな働き方が、あなたの今のライフスタイルに合いそうですか? 時間・体力・保育環境・スキルなど、自分に合った働き方を探るヒントにしてください。
6. 利用できる主な支援制度まとめ
シングルマザーが利用できる公的支援は、思っている以上に多岐にわたります。 しかし、申請しない限り受け取れないものも多く、「知らなかった」「もらえると思っていなかった」と後悔するケースも少なくありません。
ここでは、代表的な支援制度を表にまとめたうえで、実際の利用者の声や注意点も交えて紹介します。
| 制度名 | 内容/支給額例 | 所得制限 | 備考 |
| 児童扶養手当 | 月最大43,160円(第1子) | あり | 収入に応じて段階的に減額される |
| 医療費助成 | 子どもの医療費が無料〜一部負担 | あり | 自治体によって条件が異なる |
| 高等職業訓練促進給付金 | 月最大10万円+入学準備支援等 | あり | 対象資格あり(看護師・介護福祉士など) |
| ひとり親控除 | 所得控除(住民税・所得税) | なし | 年末調整または確定申告で対応 |
| 保育料減免 | 一部または全額免除 | あり | 所得+子の年齢+世帯構成で変動 |
出典:各地方自治体、厚生労働省、子ども家庭庁等(例:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000125850.pdf
「最初は何を調べたらいいかも分からなかったけれど、児童扶養手当をもらえると知って、生活が少し安心できた」 ―― 実際の利用者の声
制度はあくまで“土台”。うまく活用しながら、自分のライフスタイルに合った働き方と組み合わせることが、経済的自立の第一歩になります。
6.5. 支援制度をどう活かすか
表で紹介した制度は「知っているだけ」では何も変わりません。大切なのは、自分の状況に照らし合わせて“活かす”ことです。例えば、児童扶養手当は収入に応じて支給額が変わるので「いつ収入を上げるべきか」「どのタイミングで副業を始めるか」など、自分のライフプランとの兼ね合いを見ながら使うことが重要です。
また、高等職業訓練促進給付金のように「将来に向けたスキルアップ」を支援する制度もあります。短期的な収入よりも、中長期で年収を上げたい方には特におすすめです。
制度は“応急処置”ではなく、“成長の土台”として考えると活用の視点が変わります。
7. おわりに
年収をいきなり劇的に上げることは難しくても、”練習”を積み重ねれば必ず変化は起こります。 家計を見直すこと、制度を使いこなすこと、少しだけ学ぶこと。 どれも今日から始められる、未来の自分を助ける行動です。
「今のままじゃダメかも」と思ったその瞬間が、動き出す最高のタイミングです。 あなたの一歩が、未来の安心につながります。
一緒に、できることから始めていきましょう。