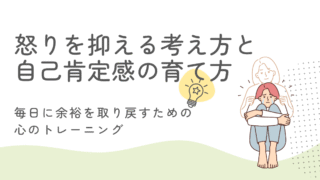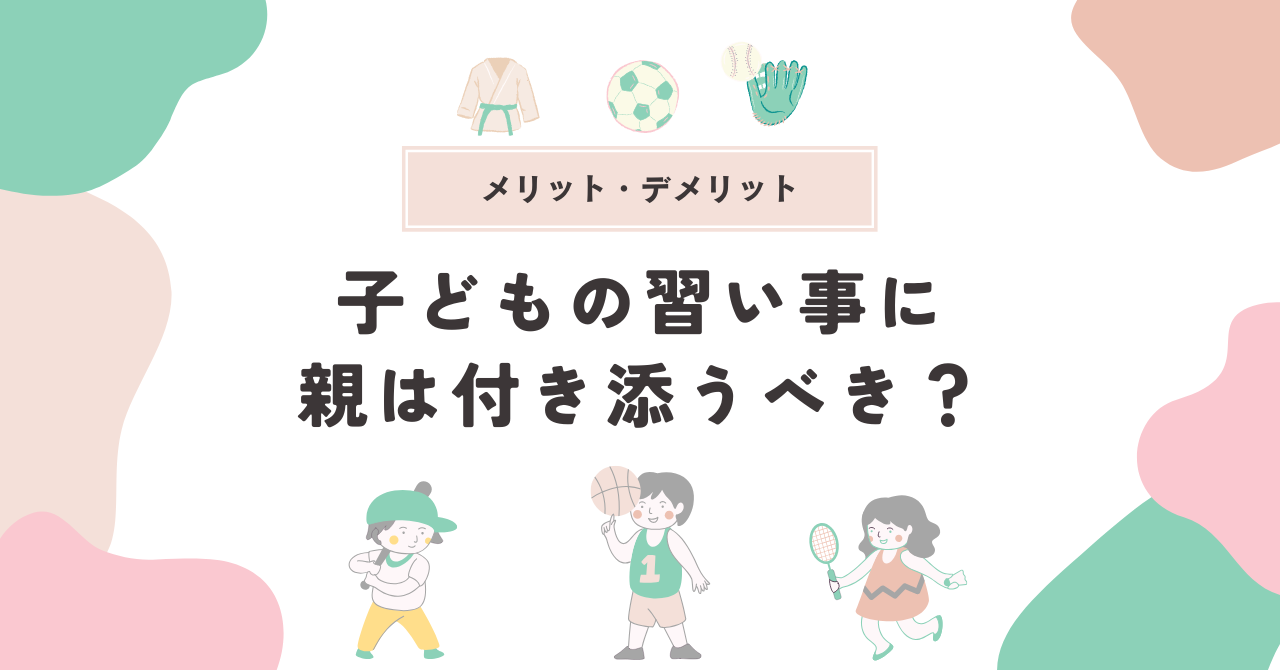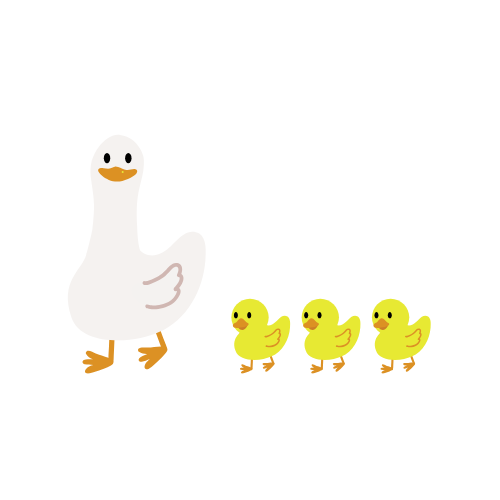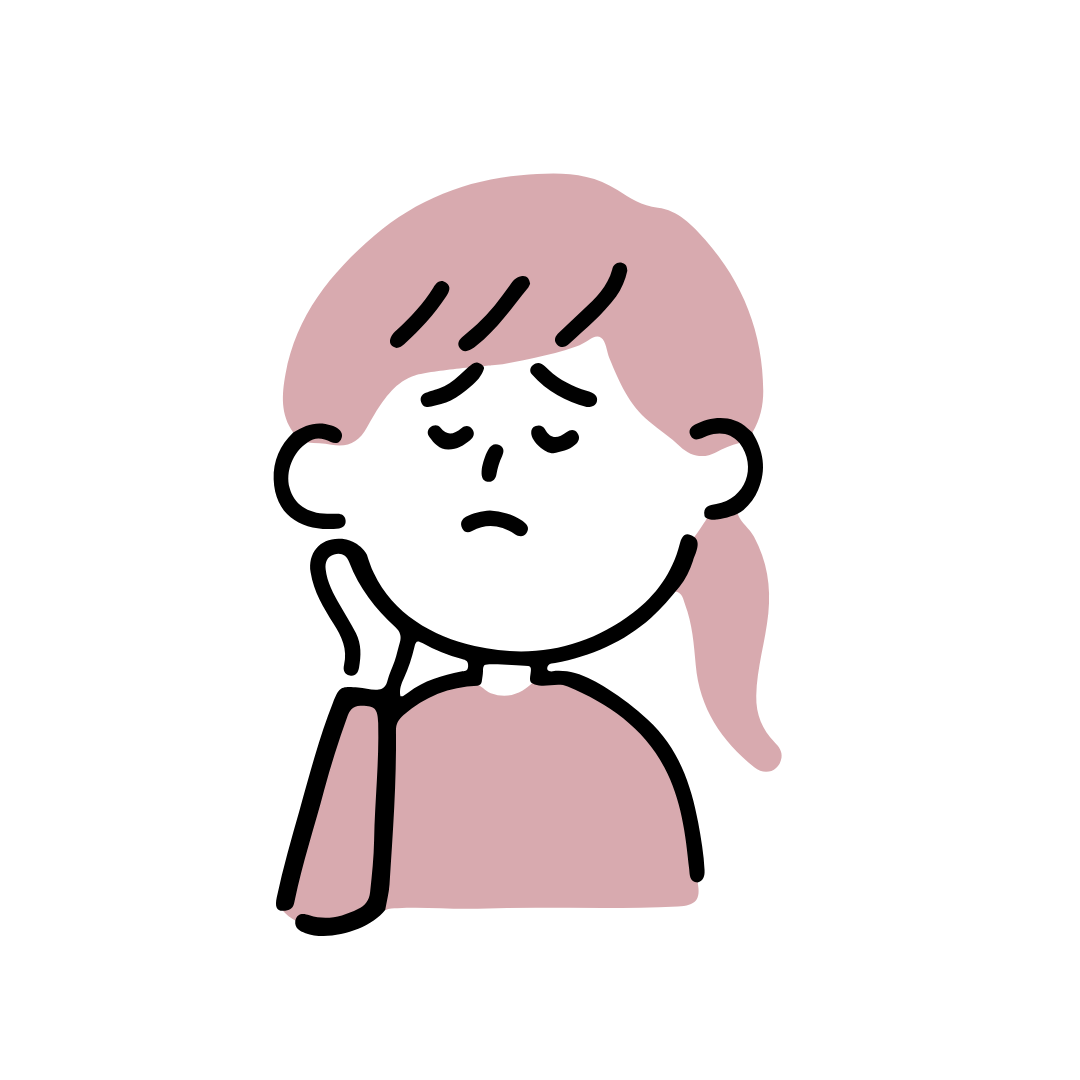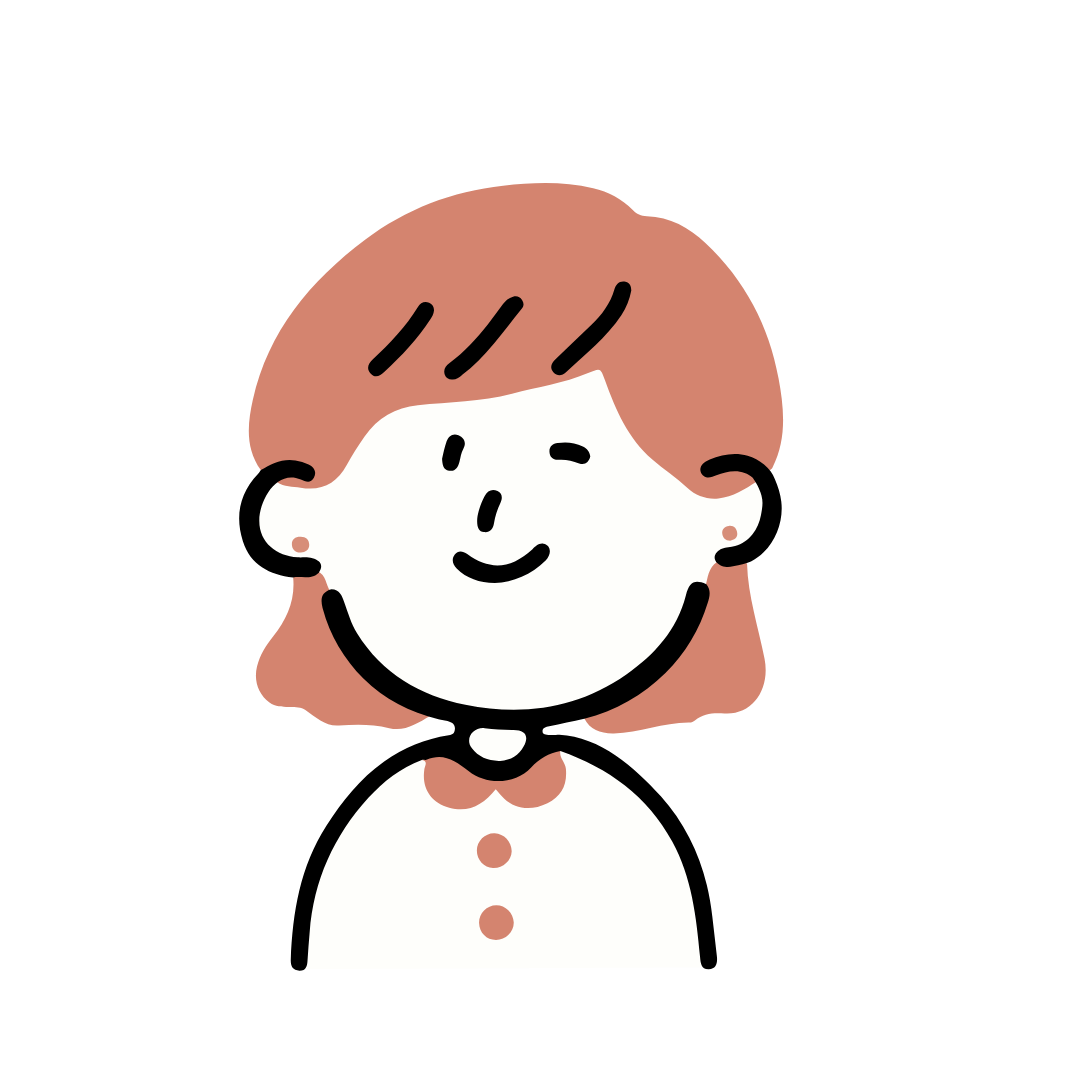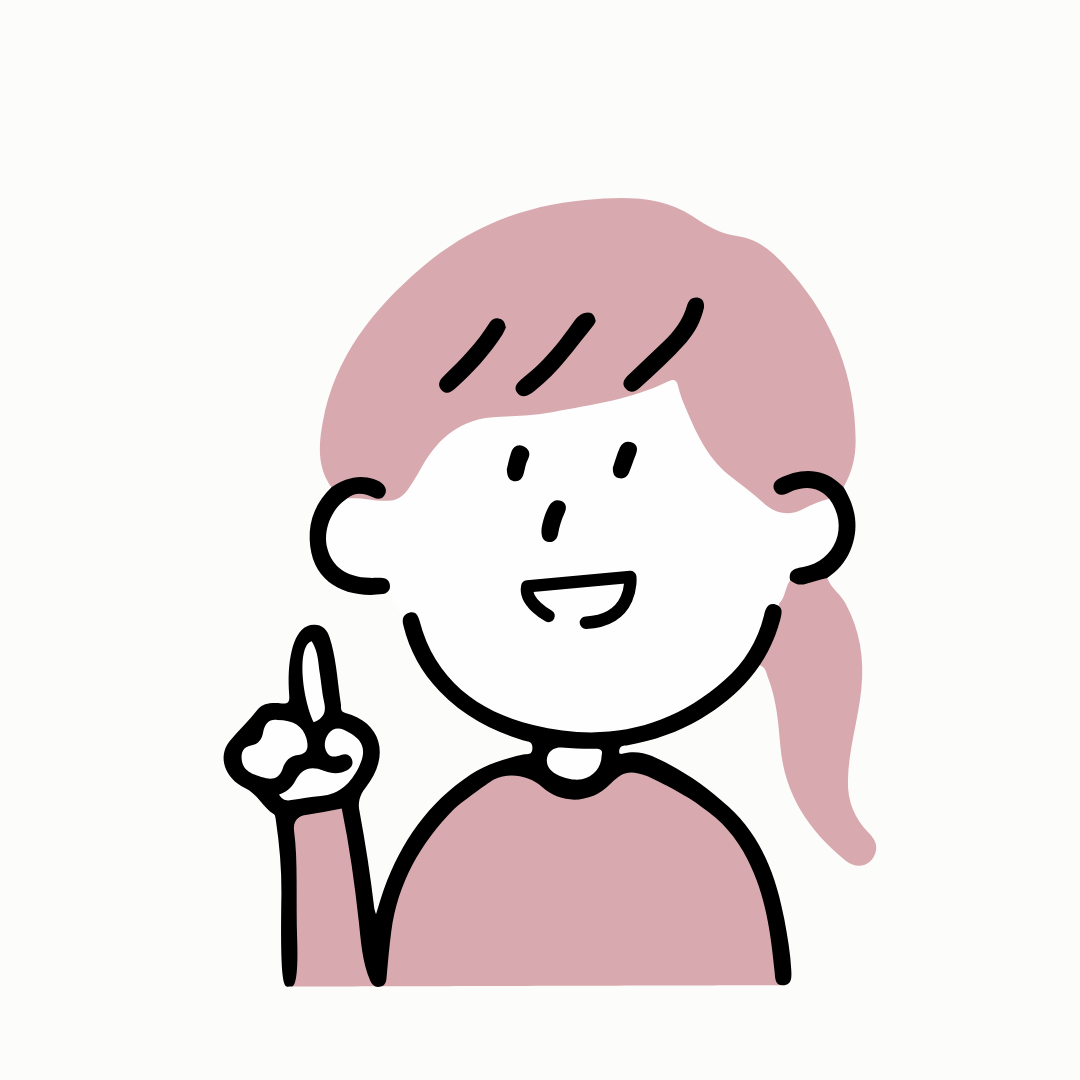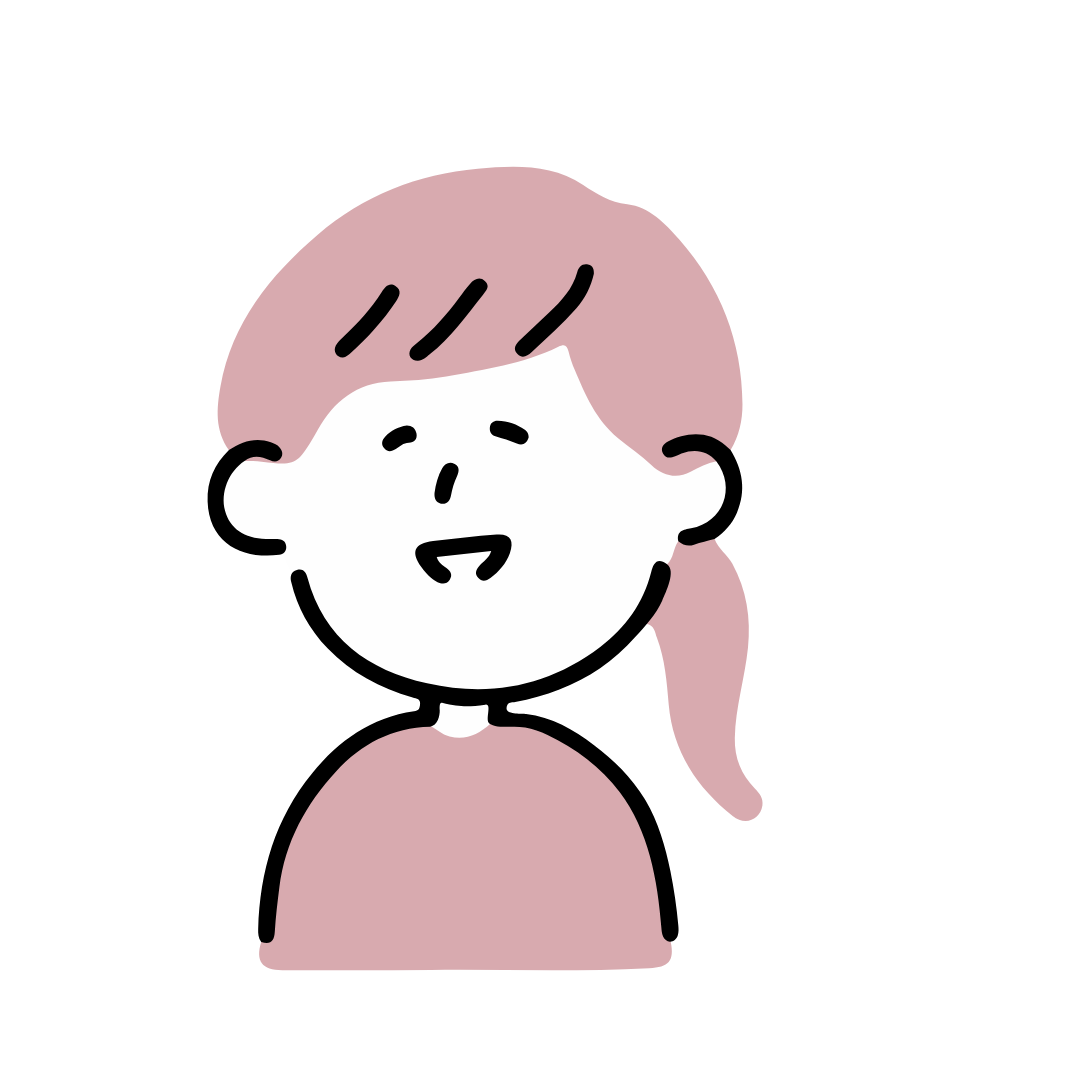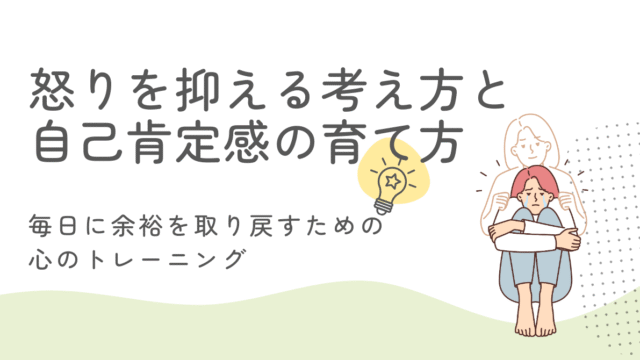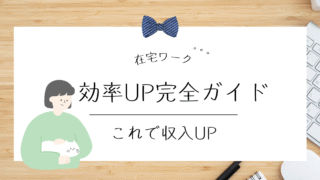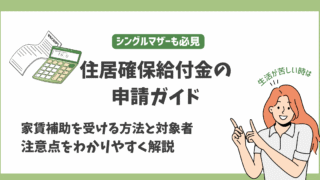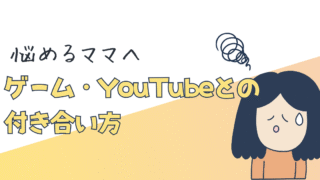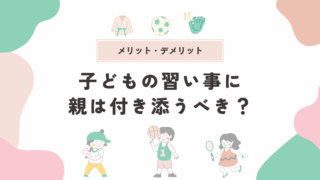はじめに:習い事と親の関わり方に悩む家庭が増えている
「習い事、付き添ったほうがいいのかな?」
そんな疑問を抱えたことのある保護者の方は少なくないはずです。 特に小学生や幼児期の子どもを持つ親にとって、子どもの習い事は「どれだけ関わるか」が思わぬ悩みの種になることがあります。
実際、「他の親が毎回付き添っているから自分も行かなきゃ…」と感じたり、「でも正直、毎回付き添うのは負担」と思ったり。
この記事では、子どもの習い事に親が付き添うべきかどうか、そのメリット・デメリットを整理しながら、家庭ごとに「ちょうどいい距離感」を見つけるヒントをお届けします。
習い事に付き添う家庭が多い理由と背景
参考: 2023年にキッズイベント実施企業「イクウェルチャイルドアカデミー」が実施したアンケート調査によると、「習い事への付き添いが精神的に負担」と感じる親は約6割にのぼりました。
出典:LEE公式サイト より引用。
「付き添い」は義務ではないにもかかわらず、多くの家庭が実践しています。その背景には、以下のような理由が考えられます。
安全面の配慮
特に未就学児や小学校低学年の子どもは、移動や着替え、トイレなどに不安があるため、親が付き添うことが自然と求められがちです。
成長を見守りたいという思い
「がんばる姿を見てあげたい」「上達の過程を共有したい」という純粋な思いから、保護者が積極的に通うケースもあります。
周囲と比べる心理
他の保護者がほぼ毎回見に来ている中、自分だけ付き添わないと「冷たい親」「関心がないのかな」と思われるのではと気になってしまうことも。
教室側の雰囲気
教室や講師によっては「親の同席が望ましい」と暗黙的な空気があり、それがプレッシャーになることも。
このように、親が付き添う理由には「必要性」だけでなく、「不安」や「気まずさ」などの感情も関係しています。
では、付き添いは“したほうがいい”のでしょうか?それとも“しなくてもいい”のでしょうか?
次章では、付き添いのメリットとデメリットを冷静に整理していきます。
熱心にやっている親御さんは、「付き添い」のイメージが強いから自分も「子どものサポート」として付き添うべきなのかな?と不安になりますよね…。
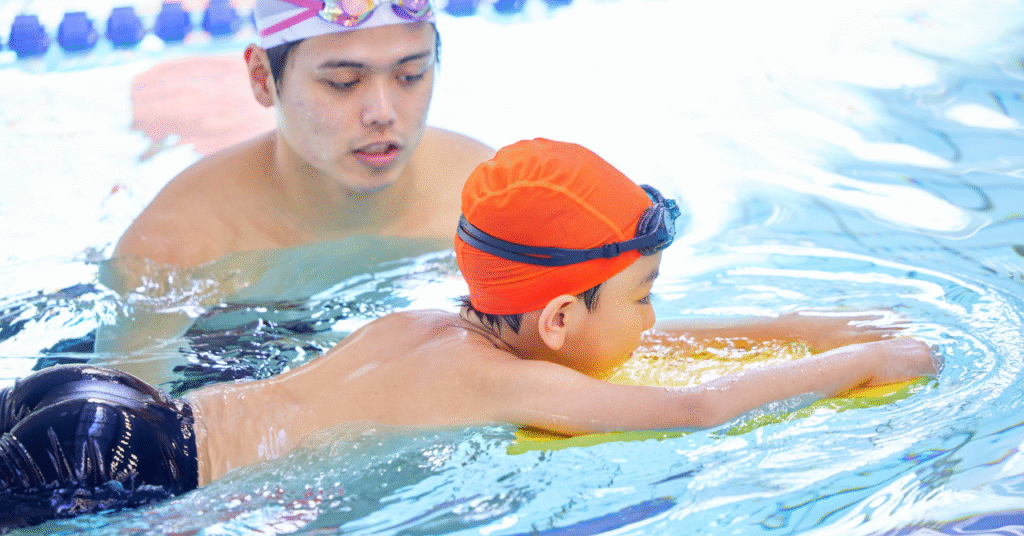
付き添いのメリットとデメリット
【メリット1】子どもの安心感につながる
親がそばにいることで、子どもは精神的に安定しやすく、特に初めての習い事では「安心して挑戦できる」環境になります。不安が強い子どもや、人見知りする子には有効です。
【メリット2】成長の過程を間近で見守れる
技術の上達や子どもの表情の変化などをリアルタイムで感じることができ、親子のコミュニケーション材料にもなります。「今日ここができるようになったね」と言葉をかけることで、モチベーションアップにもつながります。
【メリット3】講師や他の親との関係づくり
付き添っていると、講師や同じクラスの保護者と顔を合わせる機会が増え、情報交換や教室内の雰囲気把握に役立ちます。教室との信頼関係も築きやすくなります。
自分の時間があって、元気な時は「成長の一環として」見守るのもあり。
【デメリット1】時間的拘束が大きい
週に何度もある習い事に毎回付き添うのは、仕事や家事との両立を考えるとかなりの負担になります。スケジュール調整が必要になり、自分の時間が確保しづらくなることも。
【デメリット2】子どもの自立の機会を奪うことも
常に親がそばにいることで「自分でやってみる」機会が減り、自信を持つチャンスを逃してしまうこともあります。特に小学生以降は、1人でできる経験が自己肯定感につながるため注意が必要です。
【デメリット3】親のストレスやイライラの原因に
他の親との距離感や、うまくいかない我が子の姿を見てしまうことで、かえってイライラしたりプレッシャーを感じたりすることも。「付き添うのが当たり前」という雰囲気に疲弊してしまうケースもあります。
このように、付き添いには「親子の安心・信頼を育む良さ」もあれば、「親子ともに距離感が近くなりすぎる」リスクも存在します。
付き添いのメリット・デメリット【一覧表】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 子どもの安心感につながる。特に初めての習い事では精神的な支えになる。 | 時間的拘束が大きく、自分の予定や仕事に支障が出る場合がある。 |
| 成長の過程をリアルタイムで見守れ、親子の会話や共感のきっかけが増える。 | 子どもの自立を妨げてしまう可能性があり、「親なしで挑戦する力」が育ちにくい。 |
| 講師・保護者との関係づくりがしやすく、教室の雰囲気や方針も理解できる。 | 他の保護者との比較や教室の雰囲気で、親自身がストレスを感じやすくなる。 |
付き添わないという選択肢とそのメリット
親が必ず付き添わなければいけないという決まりは、ほとんどの習い事において存在しません。では、付き添わない選択をすることには、どのような利点があるのでしょうか?
【メリット1】子どもの自主性・自立心が育つ
親がいない状況でレッスンを受けることで、「自分で考えて行動する」機会が増えます。忘れ物の管理、先生との会話、ルールを守る姿勢など、すべてが自立の一歩です。
【メリット2】親の時間的・精神的な負担が減る
付き添いをやめることで、通学時間や待機時間に他の用事を済ませることができます。また、「ちゃんと見ていないといけない」というプレッシャーからも解放され、親自身の余裕も生まれます。
【メリット3】習い事が“自分の場”になる
親がいないことで、子どもにとって習い事が“親に評価される場所”から“自分が挑戦する場所”へと変わります。これは特に高学年になるにつれて大切な意識の変化です。
筆者の小4の長男は、極真空手を習っていますが、本人の意思もあり「付き添い」は一切しません。子どもの勇姿をみれるのは、大会だけですが、それも成長をグッと感じられるポイントです。
習い事のタイプ別:付き添い必要度の目安
すべての習い事に同じ対応が必要なわけではありません。内容や年齢によって、付き添いが必要かどうかは大きく異なります。ここでは、代表的なジャンル別に付き添いの必要度を整理してみましょう。
| 習い事ジャンル | 付き添い必要度 | 補足ポイント |
| 空手・柔道・剣道など(武道系) | 高〜中 | 幼少期は着替えやケガ対策で付き添いが推奨されることが多い。高学年以降は自立移行しやすい。 |
| サッカー・野球・水泳など(運動系) | 中 | 試合や練習を見たい気持ちはあるが、送迎のみの家庭も多い。チームによって親の関与度が大きく異なる。 |
| ピアノ・バイオリン・声楽など(音楽系) | 低〜中 | 幼児は送り迎えとサポートが必要。小学生以降は一人で通う子も増える。レッスン中の同席は教室による。 |
| 英語・学習塾・プログラミングなど(勉強系) | 低 | 基本的に送り迎えのみでOK。親の同席は不要なことがほとんど。 |
| バレエ・ダンス・体操など(表現系) | 中〜高 | 小さな子は衣装や準備に手がかかる。見学や発表会の観覧を重視する家庭も多い。 |
このように、「子どもの年齢」「習い事の内容」「教室の方針」によって、付き添いの必要度は異なります。
次章では、子ども自身の性格や発達段階を踏まえた判断軸について解説します。
親子の性格や発達段階による判断軸
参考: 「子どもの習い事に対する保護者の関わり方」に関する全国調査(2022年、ベネッセ教育総合研究所)によると、付き添いの頻度や理由は「子どもの性格」や「親の教育観」に大きく左右される傾向があると報告されています。 出典:ベネッセ教育総合研究所
付き添いが必要かどうかを考えるうえで、習い事のジャンルだけでなく「子ども自身の性格や発達段階」も非常に重要な要素です。また、親の性格や価値観も大きく影響します。ここでは、その判断材料を整理していきましょう。
子どものタイプ別に見る付き添い判断の目安
- 慎重・不安が強い子ども:最初の数ヶ月は付き添いをして安心感を与えつつ、徐々に距離を取っていく方法が有効です。
- 好奇心旺盛で自立心のある子ども:早い段階から1人で参加する方が自信につながりやすいです。
- 年齢が低く経験が少ない子:基本的には付き添いが必要。ただし習い事の種類によっては、1人でできるようになるタイミングを見極めることが重要です。
親の性格・価値観が与える影響
- 心配性・完璧主義な親:過度な関与で子どもの自立を妨げることも。子どもに委ねる勇気が必要。
- 放任主義の親:子どもが困っていてもサインを見落とす可能性があるため、定期的な振り返りを行うのがおすすめです。
判断のポイント
- 「親が見ていないと不安」というのは“親”か“子”どちらの感情かを整理する
- 1ヶ月ごとの子どもの様子を観察し、「自分でできた」体験を積ませていく
- 最終的には、「親がいてもいなくても頑張れる状態」を目指す
次章では、周囲の目が気になる場合の対応方法について見ていきます。
子どもの性格に合わせては大切。小5の長女は、必ず見てほしいといい。小4の長男は、断固拒否(笑)子どもに合わせていくもの大切です。
兄妹がいる家庭などは、付き添いした子どもとしない子どもで差が出ないように、その後のアフターフォローも大切です。
付き添いしない子どもには
- 「どんな様子だったのか」
- 「今日も頑張ってお疲れ様」
など、ただ行ってきただけでなく、子どもの頑張りにしっかり目を向けましょう。

周囲の目とどう向き合うか(他の親との距離感)
「周りのママたちが毎回見に来てるのに、自分だけ行かないなんて……」
そんな風に感じてしまうことはありませんか?
習い事に付き添うかどうかは本来“家庭ごとの自由な判断”であるべきですが、実際は“周囲の空気”に影響される場面が多くあります。
親同士の付き合いにストレスを感じたら
- 無理にグループに入らなくてもOK。
- 子どもが楽しく通えているなら、保護者同士の関係性に過剰に気を使う必要はありません。
「付き添い=愛情の証」ではない
他の親が付き添っているからといって、それが正解とは限りません。愛情や関心は、日々の会話やサポートでも十分伝わります。
教室との方針を確認する
習い事によっては「保護者の同席を控えてほしい」と考えるところもあります。あらかじめ方針を確認し、「見学の有無は自由」などの明示がある場合は気にしすぎず、自分たちのペースを守りましょう。
次章では、子どもから「見ててほしい」と言われたときの対応について考えていきます。
子どもが「見ててほしい」と言ったら?その時の対応法
習い事に送り出すとき、子どもが「今日は見てて!」とお願いしてくることがあります。このようなとき、どう対応すればいいのでしょうか?
年齢や性格によって背景は異なる
- 幼児〜小学校低学年の子どもは、まだ親の承認を強く求める時期。「見ててほしい」は愛情確認のサインであることが多いです。
- 小学校中〜高学年の場合、見てもらうことで“努力を認めてもらいたい”“達成感を共有したい”という思いが背景にあることも。
対応のポイント
- 無理に断らず、「15分だけ見てるね」「今日は最初だけね」と部分的に応じることで安心感を与えられます。
- 見るだけでなく、帰宅後に「今日のここすごかったね」「がんばってたね」と具体的なフィードバックを伝えると満足度が高まります。
- 毎回の付き添いが難しい場合は、ビデオ撮影や音声録音などで「見たよ」を届ける工夫も効果的です。
長期的には“見守る距離感”を育てる
「ずっと見てて」が習慣化すると、親がいないと頑張れない状態になることも。少しずつ「見なくても大丈夫」を積み重ね、子ども自身が自立して取り組めるように導くことが大切です。
付き添うときのコツと負担を減らす工夫
付き添いが必要だと感じた場合でも、親の負担が大きすぎると長くは続けられません。ここでは、無理なく付き添いを継続するための工夫を紹介します。
スマホやPCを活用して“自分時間”を作る
- 習い事の待ち時間にスマホでできる作業(メール返信、読書、学び直しなど)を準備しておく
- モバイルWi-Fiを用意して、仕事や副業をこなす“スキマ仕事時間”に
他の保護者と無理に関わらない
- 無理な会話にストレスを感じるなら、イヤホンや読書などで“そっと見守るスタンス”もOK
- 挨拶だけの距離感でも問題なし。「親同士の仲良し」は必須ではありません
送迎の工夫で時間短縮
- 家族やきょうだいで分担(例:夫と交代・祖父母がいる日はお願いする)
- 習い事と買い物などの用事を組み合わせ、効率よく時間を使う
「毎回は無理」を事前に子どもと共有する
- 最初から「毎回は行けないけど、週1は行くね」など明確なルールを作ると、子どもも安心しやすい
- 行けなかった日には帰宅後の声かけや振り返りで“関心はある”ことを伝える
まとめ:家庭ごとの“ちょうどいい付き添い距離感”を見つけるヒント
子どもの習い事への付き添いに「正解」はありません。
大切なのは、親と子それぞれが無理せず、心地よく関われるバランスを見つけていくこと。
どんなに他の家庭が付き添っていても、あなたの家庭にはあなたにしかないリズムがあります。
付き添ってもしんどい、付き添わなくても心配──そのどちらも自然な気持ちです。
最終的なポイント
- 習い事の内容や子どもの性格、家庭の生活スタイルを総合的に判断する
- 付き添いの有無を“愛情の深さ”とは切り離して考える
- 子どもの「見てて」が続くときは段階的に距離をとることも必要
- 親も子も、無理なく笑顔でいられることを最優先にする
習い事は、技術を習得するだけでなく「人としての成長」を助ける場でもあります。
親がどう関わるか──それ自体もまた、子どもの成長の糧になります。
本記事をきっかけに、あなたにとって、そしてお子さんにとって“ちょうどいい付き添い方”が見つかりますように。